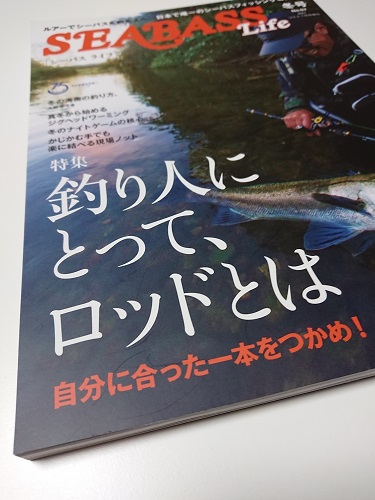
誌面の表紙に飾られた一文、『釣り人にとって、ロッドとは?』
シーバスライフ Vol.7(つり人社)に掲載された記事だ。
既に発売されているので沢山の方に読まれていると思う。
釣竿屋にとって、最高に面白いと感じた題名であると同時に、
改めて自分たちが求めるロッド観を考えさせられた内容であった。
誌面でフィールドスタッフの久保田氏は下記の様に述べている。
「デカい魚を捕るには、剛ではなくて柔でなければと…」
氏のタックルバランスを聞くと、案外ライトタックルだったりする。
昨年の末ごろメーター級を狙いに定めたタックルは、
ロッド:SWAT SW972S-ML
リール:セルテート LT4000-C
ライン:PEストロング8(1号)
リーダー:耐摩耗ショックリーダー(ナイロン16lb)
といった具合だ。
ヒット後はラインを出すと根ズレ必須の場所で、
魚を必要以上に暴れさせず適度な負荷を常に掛け続け、
徐々にターゲットの体力を奪いランディングに持ち込むスタイル。
ただし闇雲に柔らかいロッドが良いというのではなく、
フィールドで求められるタックルと道具を使いこなすスキルが必要で、
そのバランスタックルを組み立てるのも面白い部分と思っている。
シーバスロッドという括りの中で大局な見地では、
一昔前に良いとされた調子が巡り巡って現代で必要とされる流れを感じている。
私が知っている限りのロッド史でしか計ることが出来ないが、
シーバスというカテゴリーが出来た始めた頃のアクションは、
トラウトロッドをベースとした少し柔らかめのロッドが多かった。
製造技術や素材の面で、まだまだ発展途上であった事も大きな理由だが、
その頃は、ナイロンラインが主流であったし、フックは研いで使うのが当たり前。
重心移動のルアーが出て革命的だと感じたが、今と比べれば飛距離は7割位だろうか。
当時の道具は、アングラーの使い方で釣果が大きく左右していた様に思える。
そして四半世紀が過ぎた今、誰が使っても飛距離は出るし、
適度な釣果をもたらしてくれる道具も多く、情報(使い方)も溢れている。
でも、道具は変わっても釣れる魚は大きくは進化しないし、
基本的な釣り方というのは時代は変わっても同じだったりする。
高弾性で張りの強いロッド、ハイギアのリール、PEライン、フロロカーボンのリーダー、
こんなバランスにすればアングラーに伝わる感度は高いはずだ。
しかし、昔使っていたルアーを上記タックルにセットして使うと、
本来ルアーが持っている動きを引き出すことが出来ない場合もある。
柔らかめのロッド、ナイロンライン、ローギアのリールなど、
当時テストしたバランスで作られたルアーであるからだ。
特にハイギアのリールと、伸びが少ないラインは特に影響は大きいはずだ。
では、何を変えるとルアーのポテンシャルを引き出せるのか?
これを考え出すと、ロッドの選択も変わってくるのが分かると思う。
ここに一昔前のロッドとの接点が見えてくる訳だ。
最後に久保田氏の記事で、「1本の竿を長く使ったほうがいい」と述べている。
道具を使い込むことで得られることは、ネットで得られる情報よりも
アングラーとして成長できる事だという意味だ。
それに呼応するロッドに仕上げるのが私達の役目だし、
タックルバランスが分からなければ伝えていくのも同じこと。
ロッドは何を特化させ、何の汎用性が必要になってくるのか、
『進化した個性』と銘打ってプロデュースしているSWATも、
各地のフィールドで必要と思えた部分を抽出して仕上げてきた。
だけど、根底にあるネバリを基調としたアクション(調子)は、
同シリーズを立ち上げた15年前と変わっていないし、
これからも変わらない部分として継承していくと思う。
釣り人にとって、ロッドとは?
釣竿屋にとって永遠に続くテーマだ。
釣竿屋の小言でした。
Staff Funaki
JUGEMテーマ:フィッシング

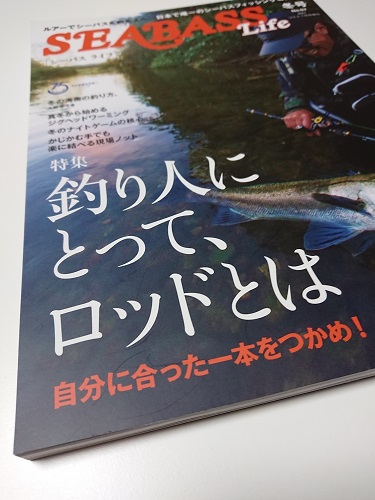


コメント